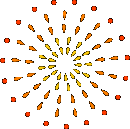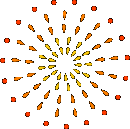<花火>
8月某日。
本日も外は猛暑です。
それでも子猫はほどよく涼しい部屋の真ん中で仰向けになって寝ておりました。
一年365日毎日そうしているのですが、子猫にとってありがたくないことに今日は飼い主という名の下僕が休みでした。
「麻貴ちゃん、たまには一緒に遊ぼうか?」
ふわふわのおなかをなでながら話しかけてみましたが、もちろん子猫は知らん顔です。
子猫は90%以上がぐーたら成分でできているので、ねこじゃらしにもネズミのおもちゃにも興味はありません。
食べて寝る以外でまずまず好きなのは、下僕のカバンや衣服でツメを研ぐことくらいでした。
「じゃあ、テレビ見ようか?」
いつもならそんな言葉も聞き流すのですが、なぜか子猫はテレビから流れてきた音に反応しました。
それは先週某所で行われた花火大会の映像です。
「なんだ、麻貴ちゃん。花火が好きなのか?」
じっと画面を見つめる子猫の瞳に飼い主という名の下僕はゆるゆるです。
「じゃあ、一緒に花火大会に行こうな」
そうは言ってみたものの、残念なことにふわふわ子猫の住む街には花火大会がありません。
「そういう時はネットで検索だぞ〜」
いつの間に来ていたのか、お祭り騒ぎが大好きな下僕その3がワクワクした顔でパソコンの前に座りました。
「どっこがいいかなぁ〜」
でも、調べれば調べるほど東京の花火大会はどこもものすごい混雑で、とても大切な子猫を連れていけるような状態ではありません。
「よし! こうなったら、俺がボーナスをはたいて―――」
下僕その1はいつものように大胆なおバカぶりを発揮していましたが、そこは比較的まともで友達思いの下僕その2が――やっぱりいつ遊びにきたのかは分かりませんでしたが――やんわりと止めました。
「やめなよ、樋渡。森宮に花火なんて、お札に火をつけて燃やすようなものだよ」
だったらそのお金でおいしいものでも買ってあげたほうが……という下僕その2の言葉に子猫の耳が反応しました。
「まあ、おいしいものはいつでも食べられるからな。けど、花火はやっぱり夏だろ?」
何より普段は食べ物にしか興味を示さない子猫が花火の写真が大写しになったパソコンの画面から目を離さないのです。
親バカ飼い主がこんなチャンスを見逃すはずはありません。
心の中は「麻貴ちゃんと花火大会♪」というフレーズで一杯でした。
「うーん……だったら、とりあえず河原にでも行って小さな花火をしてみるとか。それでもまだ物足りないみたいだったら、ちょっと遠くでも小さな花火大会を探して見にいけばいいよ」
下僕その1もその提案で妥協し、三人揃って子猫と花火をすることになったのでした。
早速、その夜。
下僕三人は花火を抱え、都心から少し離れた河原にやってきました。
手近な場所でキャンプを楽しもうとテントを張っている家族や、ドライブのついでに立ち寄ったらしいカップルなどもいて、それなりに賑やかな夜でした。
「じゃあ、まずは麻貴ちゃんの王子様席を作らないとな」
ミニ扇風機完備のスペシャルシートを用意した後、それとは別に「花火を楽しむための場所」を作り、子猫をそこに運んできて小さな花火を渡しました。
「じゃあ、火をつけるからな。気をつけるんだぞ?」
麻貴ちゃんはまだ子猫ですが、火はちっとも怖くありません。
「わかった」という顔で頷くとシュワシュワと火花をこぼす花火をブンブン振り回し、楽しそうに下僕の髪を焦がしました。
「人に向けちゃダメだぞ」
そんなことを言いながら途中までは楽しそうに花火をしていたのですが。
「麻貴ちゃん、次はどれにしようか?」
下僕が新しい花火を子猫の前に並べたその瞬間、流れてきたのは肉が焼ける音。
そう、大学生らしき人々がバーベキューを始めたのです。
おいしそうな匂いが流れてくる場所で子猫が他のものに関心を示すはずがありません。
「ごはん」
花火を投げ出し、スペシャル王子様シートに向かいました。
おかげで下僕その2以下は大喜び。
『絵日記にも書ける夏の思い出』のために一生懸命写真を撮っている下僕その1だけを置き去りにして、子猫と豪華五段重ねのお弁当を広げたのです。
とはいっても、下僕たちがお弁当を口にできるのは子猫がすっかり満腹になった後の残り物だけなのですが。
「森宮、よほどお弁当がおいしいんだね」
普段はまったりしている子猫がせっせと自分の口に好物のささみを運ぶ姿に下僕その2も思わず笑ってしまいました。
「樋渡、料理はうまいからなあ」
実際、子猫にとって下僕その1の本体はどうでもいい存在でしたが、下僕の作った食事は気に入っていました。
そんなわけで、ひたすらもぐもぐと食べ続けること20分。
満腹になった後は王子様席にひっくりかえりました。
「じゃあ、花火の続きをやろうか?」
下僕その1が声をかけても、そちらに目を遣ったのはわずか0.3秒ほどの間だけ。
「あきた」
何の遠慮もなくそう言うと、寝転がったまま当たり前のように別の物を所望しました。
「あいす」
そう、こんな夜は冷たいデザートが必須です。
「うーん、アイスは持ってこなかったな。ジュースじゃダメなの、森宮?」
下僕その2が優しい声で譲歩案を述べましたが、子猫の辞書に『容赦』という言葉はありません。
「あいす」
郊外の河原。
子猫の声が無情に響き渡りました。
けれど、少なくとも見える範囲にお店はありません。
それでも下僕その1は財布を握り締めて立ち上がりました。
「じゃあ、いい子にして待ってろよ。すぐに買ってきてやるからな?」
残りの二人に「麻貴ちゃんを頼む」と言い残すと、全速力でお店のありそうな方向へ車を走らせたのでした。
「頼むって言われても、樋渡が戻るまではどうせ寝てるだけだしね」
下僕その2は微笑みながら子猫を見下ろし、
「いーじゃん。俺らもアイス食えるしー。待ってるだけだしー」
下僕その3はビールを片手にお弁当をつつきながらうきうきしてその1の帰りを待つことにしました。
でも。
世の中はそんなに甘くはありませんでした。
「なんでアイス2本だけなんだよー」
戻ってきた下僕の手にはアイスが二つ。
もちろん子猫と飼い主である下僕その1の分です。
「麻貴ちゃんと二人で仲良く一つでもよかったんだけどな」
世界の中心がふわふわ子猫である下僕その1は当然のようにそう答えました。
そんなわけで。
「ほら、麻貴ちゃんの好きなアイスだぞ」
その後は二人だけの世界。
子猫はアイスを、下僕その1はアイスをおいしそうに食べる子猫を満喫し、下僕その1の世界から取り残されたその2とその3は二人でやさぐれながらまた新たなビールを取り出しました。
「森宮ったらアイスに心が奪われてて、樋渡が抱っこしてなでまくってるのに気付いていないよね」
「いんじゃないのー? そんなことでもないと森宮みたいなネコの飼い主なんてやってらんないしー」
俺なら絶対ヤだね、と言い切る下僕その3に苦笑いしながら、その2はふと我が身を振り返りました。
「それよりさ……俺たちはこれでいいのかな?」
けれど、下僕その2とは対照的に下僕その3は特に何も思わない顔で夜空に向かって乾杯をしました。
「俺は別にいいぞー。ビールうまーい。はい進藤君ももう一杯!」
楽しそうな友人と、河原に心地よく吹き抜ける夜風。
下僕その2もとりあえずこんな週末も悪くはないという気持ちになりました。
「でも、樋渡は運転あるからビール飲めなくて可哀想だよね」
「いんじゃないの? どう見ても一番幸せそうなのアイツだろー」
そう言われて、ちらりと隣に目をやると子猫は膝の上でご就寝。
それを見下ろす飼い主は半溶け状態。
確かに『可哀想』などという言葉とは無縁の世界でした。
「……じゃあ、いいか」
なんとなく流されているような気がしつつも、下僕その2はまた新しいビールを手に取りました。
「はい、じゃ、もう一回、しんどーくんにかんぱーい!」
空にはキラキラと瞬く星。
頬をかすめるやわらかな風、水の流れる音。
「いい夜だなー。ここでヤリてー」
空き缶の増量と共にアルコールもほどよく回り、そろそろ世間の目も冷たくなろうかという頃。
「あれー、車はどこだー?」
河原には取り残された下僕が二人。
「……置いてかれたみたいだね」
傍らには虫除けスプレーと蚊取り線香。
計画的な犯行だということは明らかでした。
「樋渡、気が利くー」
「……それはちょっと違うよね」
結局、下僕その3は睡魔に襲われ、何の疑問も持たずにその場で撃沈。
そんな友人を置いていくことができず、下僕その2は夜空を見上げてふうっと大きく息を吐きました。
「……中西の方がおいしそうだから、俺は蚊に刺されたりしないよね」
そう呟きつつ念入りにスプレーで肌をガードしながら、下僕その2の夏の夜は更けていったのでした。
|