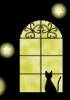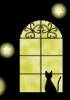|
【フロア見習い:まもネコのハロウィンキャンペーン】
10月も残り半分となった今日、新宿裏通りのクラブ『Type-B』ではハロウィンイベントの準備のまっ最中でした。
「こんにちはー」
お店に来るまでの間に何度か転んでしまったせいで、子猫は何となくほこりっぽくなっていました。
「えらく汚れてんな。今日は何につまずいたんだ?」
オーナーは子猫の首根っこをつまみ上げると、業務用のワゴンの上に乗せ、猫用の使い捨てタオルで耳の先からしっぽまで綺麗にしました。
そして、ドライヤーで乾かした後、オレンジ色の服を着せました。
「マモにはやっぱりこういうのが似合うな」
「これなに?」
「ジャック・オー・ランタンだ」
「かっこいいかも!」と言って子猫はとても喜びましたが、実際は『ジャック・オー・ランタンのきぐるみ』とでも言えばいいでしょうか。
目鼻を切り抜いたカボチャ型のフードがついたオレンジ色のつなぎでした。
「ぐれちゃんはなんの服?」
「魔法使いだって」
黒い三角の帽子に紫のリボン、裏地が紫の短い黒マント。
灰色の子猫にはとてもよく似合っていましたが、魔法使いそのものというよりは『一番下っ端の見習い』という感じです。
他にもおばけ風とか、包帯服とか、シルクハットとか、海賊とか、赤いチョッキとか、白い手袋とか、白いお腹とポケットつきの青いきぐるみとか、片方の耳だけに大きなリボンとか、時代劇みたいな兜とか、みんないろいろな服を着せられています。
何のひねりもない衣装ばかりですが、「この『いかにも感』がいいんだよ」と安易なオーナーは開き直っていました。
「ねー、これなんて読むの?」
テーブルに置かれていたコースターもいつもと違って英語の字が書かれています。
オレンジかぼちゃ姿の子猫が首を傾げました。
「ハッピー・ハロウィーン」
一番近くにいたオーナーが答えてあげましたが、「どうせ聞いてもわからないだろ」と思っているのがありありとわかる態度でした。
「はっぴりあおりん?」
「ハッピーは知ってるだろ。それと『ハロウィン』だ」
指でたどっていたら、「読む方向が反対ですよ」と、後ろを通りかかったレジ係が教えてくれました。
「ふーん、そうなんだー。ねー、それ何の服?」
「バーテンダーです」
レジ係は黒のベストにシンプルなネクタイというシックな装いでしたが、かぼちゃ服の子猫にはそれが何なのかわかりませんでした。
しばらく考えてから、
「バッテンダーは何のおばけ?」
そう尋ねましたが、その時にはもうレジ係は自分の持ち場に戻ったあとでした。
「かいじゅうの名前みたいだよね? どんなのか知ってる?」
しかたなく手近なところに質問を投げたのですが、子猫の相手をするのが面倒になった店主はサラッと流して仕事の指示だけをすることにしました。
「それはいいから。さっき教えたのだけはちゃんと覚えろよ。お客が入ってきたら、『トリック・オア・トリート』。わかったか?」
「りっくあーりーと?」
「マモ、頭だけかと思ったら耳も悪いのか?」
「そんなことないはずだけどなー」
中野の足音だったらものすごーく遠くても聞こえるよ、と答えようとして、小さな口を開けかけたとき、青年医師が優しく子猫をなでました。
「煙草くわえたままで話されたら、誰だって聞き取りにくいですよ」
穏やかな先生は子猫たちにも大人気です。
今日も本業である人間患者の診療時間のあとに、お腹が痛いという新入り子猫の様子を見に来たのでした。
「ああ、啓ちゃん。チビの腹具合どうだった? 昨日、健康診断してもらった時はなんともなかったのに」
子猫は昨日拾われたばかり。
すぐに動物病院でチェックをしてもらい、「病気なし、虫なし。血液検査正常。いたって健康です」と太鼓判を押されたのにもかかわらず、今日の夕方になって突然「おなかがいたい」と泣き出したのです。
「原因は食べすぎですね。うまく吐き戻すこともできなくて苦しくなってしまったんでしょう」
まだ小さいですからね、と猫用のベッドで丸くなっている子猫の背中をやさしくなでてあげました。
青年医師が働いている場所は人間用の小さな診療所ですが、困ったことに本当に具合の悪い人はあまり来ません。
常連患者さんたちはたいていいつも元気なので、今夜はお店に顔を出していました。
飾り付けの手伝いと、お店をにぎやかに見せるための要員を兼ねていたのです。
「そういうのを『さくら』って言うんだって北川が教えてくれたけど、なんで秋なのにさくらなのかちっともわからないんだー」
誰でもいいから教えてくれないかなとあたりを見回したのですが、近くにいたのは子猫ばかりで誰も答えを知りませんでした。
「まあ、それはいいから。マモは『トリック・オア・トリート』だけ覚えろよ」
「……なんかむずかしいかも。とりっくおあとりーととりっくおあとりーとりっくあー……あー?」
練習さえままならない子猫を見かねたオーナーは究極の解決方法を教えます。
「そしたらアレだな。『何度も聞いたけど覚えられなかった』って言って客に教えてもらえ。子猫だし、バカなところも可愛いって思うやつがいるはずだ」
「わかったー」
頭のよさそうな人に聞いてみようとつぶやく子猫の額を、店主は笑いながらツンとつつきました。
そうでなくてもバランスが悪い子猫はいとも簡単にソファの上にコロンと転がってしまいます。
「もう、北川さんは……どうしてそうやってマモル君にだけちょっかい出すんです?」
青年医師が少し厳しい口調で店主をにらみましたが、
「他のヤツよりどんくさいから。それに、俺、他人のものをいじったり取ったりするのが好きなんだ」
しれっとした顔でそんな返事をしただけでした。
「本当に性格悪いですよね」
思わずつぶやいてしまいましたが、飾り付けを手伝っていた人間の大人たちはみんな「何を今さら」という顔をしただけでした。
そんな会話の傍らで着々と装飾は進んでいきます。
ハロウィンイベントを控えた今夜は普段より女性客が多いはず、という理由から「おしゃれ感」より「癒し」を重視した内装にしていました。
「いいんじゃないか? アットホームな感じで」
インテリアを任された全員がオヤジだったとは思えないほど可愛らしい仕上がりとなり、腕組みをして見守っていたオーナーも満足げです。
「そろそろ開店時間だな。マモも心の準備しておけよ」
「どんなー?」
「客が来たら走って出迎える。で、元気に挨拶」
「うん! こんにちは!」
「いらっしゃいませ、だろ」
そうじゃなかったとしても、せめて「こんばんは」にしろと言われ、子猫は一人で練習を始めました。
「走って、ドアに行って、いらっしゃいませー。走って、ドアのとこでーえっとー」
イメージトレーニングなどという言葉を知らないので、何度も出入口とフロアを往復し、つまずいたり転んだりしている子猫を見ながら店主がまた盛大に笑いました。
「北川さん、失礼ですよ。一生懸命なのに」
「一生懸命だからおかしいんだろ。だいたい、あんなに派手に転がってんのに頭打ったりしないのか?」
「子猫は意外と大丈夫なんですよ。体も柔らかいですから」
真面目に答える医師の言葉などすっかり聞き流した挙句、「ああそうか」と一人で頷きました。
「何度も頭打ってるからあんなになっちまったんだな。打ち所が悪くてそのうち天国行きになりそうだ」
仮にも自分の店の従業員に対して言うセリフではありません。
でも、ここでそれに腹を立てる者はいませんでした。
「マモル君は大丈夫ですよ。ちゃんと神様が見ていてくれますから」
青年医師が「だって護っていう名前なんですよ?」とにっこり微笑むと、店主はソファにふんぞり返ってお腹をかかえました。
「啓ちゃんってクリスチャンだっけ?」
青年が「いいえ」と答える前に廊下から戻ってきた子猫が「知ってる!」と短い手を挙げてテーブルの上に飛び乗りました。
「なんだ、マモ、クリスチャンの意味分かるのか?」
「うん。お客さんのねー、かばんのねー、名前なんだよ」
書いてあるの見せてもらったんだと得意気に胸を張る子猫に呆れながら、店主が隣りを見遣ります。
「なんの話か分かるか?」
「ブランド名か何かじゃないですか?」
「ああ、なるほどな」
そんな言葉で軽く流したあと、さらりともとの話に戻しました。
「まあ、それはいいとして。啓ちゃん、マジで宗教は? 墓は教会じゃなくて寺? 八百万の神とか言うなよ?」
「僕に信仰心があるように見えますか?」
「いや。だから聞いてるんだろ。ちなみに俺は何一つ信じちゃいないが」
青年医師は「そうでしょうね」と冷たく言い放ってから、こう付け足しました。
「マモル君のが何の神様かは僕にも分からないですけど、最近はちょっと信じてもいいかなって思ってるんですよ」
「どうしちゃったんだよ。らしくない」
何かを問うような目で医師を一瞥しましたが、さすがにそろそろ自分も仕事をしなければと思ったのか、その先は言いませんでした。
いったん姿を消すと、小洒落た電気のキャンドルを持って帰ってきました。
「信じなくても別にいいですよ。マモル君にはちゃんと神様がついていて、お願い事を叶えてくれてるんですから」
「ね?」と顔を覗き込まれた子猫がぱっと顔を輝かせました。
「うん。もうずっと中野の家で寝かせてもらってるんだー」
子猫の言葉に常連客たちの口元が緩みます。
喜ぶ子猫の様子が微笑ましいのはもちろんですが、どちらかというと毎晩子猫を連れて帰る男の顔を思い出して、つい笑ってしまったのです。
「でもね、それってホントは闇医者の魔法なんだよ」
ないしょばなしでもするかのように小さな声で告げた子猫の大真面目な顔を見て、店主は再び笑い出しました。
そして、自分を見上げている子猫のおでこを人差し指でぐいっと押して後ろに倒しました。
ころん、とテーブルに転がる様子がまるっきり毛玉のようだと言ってまた笑い、さらに転がしてテーブルの下に落そうとしたところを医師に止められました。
「北川さん。だから、どうしてそういうことを―――」
どんなに冷たい声で言われても店主に反省の色はありません。
「まあ、魔法使い啓ちゃんの実力のほどはともかく、どこかにいる何かの神様に願い事してみるのもたまにはいいかもしれんな」
片手じゃ足りないほど沢山あるからと左右の手を広げる店主に向かって、青年医師は一度ニッコリ笑うと、少々冷たい声で言いました。
「北川さんじゃ無理だと思いますよ。神様は良い子のお願いしか叶えてくれませんから」
死んだら地獄へ落ちることが決まってる人間の願い事なんて聞くわけないじゃないですか、と笑いながら吐き捨てる様子を見て、
「……普段は白衣の天使のくせに、意外と黒いこと言うんだな」
さすがの店主も少々苦い笑いを浮かべたのでした。
大人たちが荒んだ会話をする傍らで、ひっくり返されたあともゴロゴロ転がっていた子猫は、雇い主の腕時計の長い針と短い針がちょうど重なる瞬間をみようと、じっと目をこらしていました。
ほんの少し前まではまだまだ夕方という時刻でしたが、10月の終わりともなれば日没は駆け足です。
普通ならなんとなく物悲しい気分になるところですが、お金が大好きな店主にとっては大変わくわくする季節でした。
なぜなら、勤勉な大人たちのほとんどは明るいうちにお酒を飲もうとは思わないからです。
「こんにちはぁ。看板にハロウィンイベントって書いてあったの見たんですけど、もうお店開いてますか?」
ミニカウンターを拭いていたレジ係がしっぽをピンとさせて振り返ります。
今日最初のお客さんは優しそうなお姉さんたち4名で、中の一人は月に何回かは必ず訪れてくれる常連さんでした。
それまで床やソファで遊んでいた子猫たちの耳がいっせいにピクっと反応し、トトトトトッと軽い足取りで走っていきます。
「トリック・オア・トリート!」
レジの手前あたりで「きゃあ」「かわいい!」という歓声と、「にゃー」「みゅう」という子猫たちの挨拶が入り交じります。
「お客様の衣装や小物の貸出し、および猫用のお菓子の販売はこちらで承ります。お好きなものをお選びください」
真面目な顔で説明をしていたレジの係も「かわいい」「賢そう」「つやつやしてる」などと好き勝手な感想を述べられながら、思いっきりなでられました。
お客様はそれぞれ気に入ったケープや帽子、耳のついたカチューシャなどを選んでからミニカウンターへ。
普段ならボトルが並ぶ棚には、ふた付きの透明なボックスが30個ほど鎮座していました。
「あー、これ猫の形してる」
「お魚っぽい形もかわいいよね」
「ちょっとおいしそう」
「人間が食べても平気なのかな?」
口々に言いながら、猫用のおやつを購入します。
フロアに現われたお姉さんたちの手には、小分けにしてリボンをかけた愛らしい模様の袋がいくつも握られていました。
「今日は儲かりそうだな。マモ、ちゃんと接客しろよ。きれいなお姉さんには、『かっこいいサラリーマンのお客さんもたくさん来ます』って言うんだぞ」
「うん、わかった」
格好の良いスーツの人たちが来るのは、もっとずっと遅い時間です。
でも、そのうちに来るのはたぶん本当なので、言われたとおりに伝えることにしました。
今日から月末まではハロウィンイベント。
店の前に置かれた看板とオレンジかぼちゃの飾りに誘われて、次々とお客さんがやってきます。
アルバイトの子猫たちはお客さんとおそろいの服を着て写真を撮り、いっしょにゲームをして、間にそれぞれ大好きなおやつをもらいます。
お酒を飲んでいるだけの日よりも売り上げはずっと多いので、オーナーも大喜び。お店は普段の何倍も楽しい雰囲気でした。
「なあ、啓ちゃん。中野が来たら何の仮装させようか?」
上機嫌で青年医師にそんな相談までしましたが。
「僕はその前に帰りますから。王子様の羽帽子でもかぼちゃパンツでもご自由に勧めてください」
やはり冷たい返事しかしてもらえませんでした。
「中野はスーツのときが一番かっこいいと思うなぁ」
そうつぶやいたあと子猫はしばらく考えていましたが、
「……でも、たまには他の服も見てみたいかも」
ほんの少しだけそう思ったりもしました。
「中野は何着ても同じだろ」
どうせヤのつく職業にしか見えないと笑う店主の隣で、子猫は時計を眺めて思案顔です。
「大丈夫かなぁ……」
お客さんたちの笑い声が楽しそうに響く中、その時間まで自分が起きていられるかということばかりが気になる子猫なのでした。
-Fin-
|