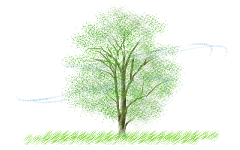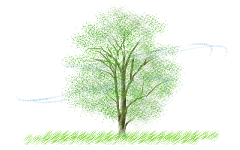「で、部屋の外はいきなり林で、しかも、その先も延々と林なんだな」
自分では相当歩いたと思うんだけど、俺と片嶋を取り巻いている風景はまったく変わらない木々の中。
何よりもドアを出た途端に建物の姿さえ見えなくなったのが、いかにもって感じだった。
「おなかが空いたらクッキーがありますよ」
片嶋がベストのポケットから取り出したのはさきほどのアイテムの一つであるクッキーの缶。
「っていうか、よくそんなデカイものが入るよな?」
「……最初から入っていたんです」
なんとなく、未来から来た機械仕掛けの青い猫を思い出す。
それ以上に、それなら懐中時計も入るだろうと思うんだが。
「でも、時計は入らないんです」
片嶋が言うんだから、そうなんだろう。
そういうことにして、それ以上は突っ込まないことにしておいた。
その時計はと言えば、懐中時計なのに時々しゃべる。
とても人間的な声で「あと何時間何分何秒です。少し急いだ方がいいかもしれません」と世話を焼いてくれるのだ。
「でも、こんなに歩いてるのに、時間はあんまり経ってないんだな」
「そうですね。すべてが適当って感じです」
片嶋らしい不満が辺りに響き渡ると、時計は自らパタンと蓋を閉じた。
「それにしても、風景がまったく変わらないよな」
時計がどれくらい進んだのかは分からないが、俺の感覚ではもう一時間は歩いているだろう。
「そうですね」
片嶋はときどき自分で歩き、たまには目線でだっこをねだったりしながら、それなりに楽しそうにしいた。
「あとどれくらいでここを出られるんだろうな」
疲れることはなかったが、そろそろ飽きてきたなと思い始めた時、木の上にふわふわしたものを発見した。
「あれって……」
片嶋も興味津々で見上げていたから、そっと抱き上げて近寄ってみた。
「アリスならチェシャ猫というところでしょうか」
「アリスのネコって笑ってるんじゃないのか?」
俺たちの声に反応して薄目を開けたネコは小さくてふわふわで、絵本で見るチェシャ猫よりもずっと可愛かったが、なぜかとてもダルそうに垂れていた。
そして、目だけを動かして俺たちを確認した後で口にしたセリフが。
「けっ」
ちびでフワフワな子猫。
なのに、『けっ』っていうセリフはどうなんだろう。
片嶋も普段は可愛いことなんて言わないが、それにしてもこれはありえない。
「……多少不細工でも子猫は性格が可愛いほうがいいよな」
思わずそう呟いたら、片嶋の小さな手が俺の口に当てられ、ついでに「しっ、ダメです」と怒られた。
「なんで?」
「誰かに見つかったら、『俺の可愛い麻貴ちゃんになんてことを言うんだ』の刑ですよ」
片嶋はポケットから出した本を凝視しながらそんなことを言った。
そこにはふわふわチビ猫のイラストと『世界の中心』というコメントが書かれていたが。
それよりも。
「それってどんな刑なんだ?」
どこかにその説明が書いてないものだろうかとページをめくった時、突然薮がガサガサ動いて、黒いスーツ姿の男が現れた。
「こんにちは。この辺りの方ですか?」
片嶋が声をかけたが、俺たちのことなど視界に入っていないらしく、一目散に子猫のいる木に向かって行く。
見た目は普通のサラリーマンだが、どうも様子がおかしい。
それも俺の目の前30センチ先を無言で思い切り横切るほどの慌て様。
俺も片嶋も彼の視界にはまったく存在していないかのようなその態度にうっかり「え?」と呟いてしまったほどだ。
「俺たちって、もしかしてこっちの人間には見えないのか?」
きっとそうなんだろうと思ったのに、片嶋からは「そうじゃないようです」というキリリとした否定が。
ついでに。
「彼についても本に載っていました」
めくったばかりのページに黒いスーツの男。『職業:下僕』と添えられていた。
「……下僕ってどういう仕事なんだろうな」
それにしても微妙な説明書きだと思うのは俺だけなんだろうか。
そんな会話の合間にスーツの男はふわふわ子猫が寝ている木の下にたどり着いた。
「やっと見つけた。探したんだぞ。おうちに帰ろう。な?」
そう言いながら、ものすごく緩んだ笑顔で子猫を抱き下ろすべく両手を差し出したけど。
当の子猫はえらく機嫌が悪かったようで、差しのべられた手にいきなりビシバシビシシシっといい音のするパンチをお見舞いしていた。
「あれって飼い猫だったのか……」
それにしてもずいぶんと懐いていないようだが。
もしかしたら、飼い主の振りをした誘拐犯とか……。
そんなことまで邪推した俺に片嶋はキリリとした顔を向けて、思いきり「違います」と否定した。
「猫が主人で、迎えに来たのが召使いのようです」
なるほど。猫の『下僕』なのか。スーツの男が背負っている大きなバッグからは縁取りにゴージャスな刺繍を施したふかふかの座布団がはみ出していた。
そして、その一辺には「麻貴ちゃん専用」の金糸の刺繍まで。
とりあえずその状況から、子猫が「麻貴ちゃん」という名前で、そこに乗せて連れ帰るつもりなんだろうってことはわかったけど。
「なんていうか、ちょっと変だな……」
子猫もだけど。
男も変だ。
「……まあ、いいか」
どこをとっても変なことしか起こらない場所だ。
ネコも下僕もこの状態が標準仕様なんだろう。
一人で勝手に納得して、未だに木の上で寝ている子猫に目を遣った。
「麻貴ちゃん」という名前からすると女の子のようだが、態度を見ているとなんとなく違うような気もする。
というか、ふてぶてし過ぎて、そもそも子猫らしくない。
もともとそういう性格なのかもしれないし、そういう種類のネコなのかもしれないけど。
「猫としてはちょっと微妙だよな」
「そうですね」
……本当のことを言うと、片嶋もちょっと微妙なところはあるんだが。
それでも片嶋は全体的に可愛いから、それほど気にならない。
「それにしても、下僕が主人を『俺の麻貴ちゃん』なんて呼ぶか?」
なんだかな、と思いながら聞いたら、
「いろんな意味で逸脱しているんでしょう」
きっぱりした答えが返ってきた。
確かに下僕らしき男はややイってしまってる感がある。
「だからってネコをあれだけ溺愛するってどうなんだろうな……」
うっかりそう呟いてしまったんだが、その後で自分の大失言に気付いた。
ヤバイと思いつつ、ちらりと視線を投げると片嶋が冷たい目で見上げていて。
「わりい。片嶋もネコだってこと忘れてた。おまえってなんかネコっていう気がしないんだよな」
実際そうなんだが、片嶋はちょっと複雑な表情のまま。
「……別に構いません」
そう答えたけど明らかに拗ねている様子で。
口はへの字。眉も寄っていて、わずかに涙目。
「悪かったって。片嶋のことは俺だって―――」
何度も弁解したけど。
「いいです。気にしてませんから」
もう何を言ってもダメって感じだった。
そういうところが、片嶋なんだよな。
……まあ、それも可愛いんだけど。

|