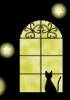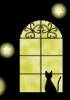|
【会計係:ネコ片嶋のお客様】
「いらっしゃいませ、鹿島様」
今宵もキリリとした佇まいでレジ台から挨拶をしたのは気品漂うスマートな猫。
「やあ、片嶋君、こんばんは。今日もいい毛艶だね。あとで夕刊のトップ記事について君の意見を聞かせてもらいたいんだが、どうかな」
常連客も高そうなスーツに身を包んだ紳士です。
「はい、喜んで。では、後ほどお席にお伺いします」
片嶋君の接客は礼儀正しくて若干愛想がありません。
でも、そんな片嶋君に作ってもらったカクテルを飲みつつ、経済や政治の動向について語り合いたいというお客様は大変多いのです。
たいてい品が良く、人生の成功者。
しかもたいそうなお金持ちなので北川オーナーは片嶋君のお客様が大好きでした。
「ショウちゃん、ものすごい玉の輿に乗って店に寄付とかしてくれよ」
ことあるごとにオーナーにそんなことを言われていましたが、片嶋君のお気に入りはごくごく普通の若いサラリーマンです。
同年代の会社員に比べたら多少は良い給料をもらっていましたが、特にお金持ちというわけではありません。
「生憎ですが、あくまでも自分の仕事はレジ係で、結婚相手もしくは養子先を探しているわけではありませんので」
そんな返事をしつつ、片嶋君はレジ台にキリリと座って意中の人を待つのです。
こんな生真面目なネコなので、好きになった相手にもとても控えめな性格でした。
二人で話をすることがあっても、
『猫と暮らしてみようと思ったことはありませんか?』
そんなひとことが言えずにいました。
ここにいるのは仕事のため。
でも、やっぱり好きな人と一緒に暮らしてみたいと思っていました。
そして、今日は金曜日。
サラリーマンが羽を伸ばすにはちょうど良い夜です。
期待に胸を膨らませながらじっと入り口を見つめる片嶋君の願いは届いたようで、静かに開いたドアから入ってきたのは待ち侘びた相手でした。
「いらっしゃいませ、桐野様」
「こんばんは、片嶋。けど、俺を呼ぶ時は『様』なんてつけなくていいよ」
「……では、桐野さん」
呼びながら、片嶋君が少しだけドキドキしていたことは内緒です。
そんな気持ちを悟られないように、わざとクールを装っていましたが、片嶋君の意中の相手は細かいことには気付かないタイプでした。
「な、片嶋。一人でレジ台に座ってるの、飽きないか?」
暢気な声でそんな質問をしながら、レジ台に置いてあった新聞をペラリとめくります。
「ここが好きなんです。手の空いている時には本や新聞を読んで勉強できますから」
片嶋君は自分の持ち場がとても気に入っていました。
見晴らしもよく、空調も快適。
居心地がよいのはもちろんでしたが、一番の理由は他にありました。
レジ台の隣はウェイティングスペース。
小さなバーカウンターが作られていて、フロアに通される前にここでカクテルを飲むお客様もいます。
何よりも、そこは片嶋君の大好きな人のお気に入りの席でもありました。
「ここでいいよ。俺、ソファよりカウンターが好きなんだ」
思っていた通り、今日もそこに浅く腰かけて夕刊を広げます。
「では、何かお作りしましょうか?」
片嶋君が待ち焦がれていた二人きりの時間です。
「じゃあ、任せるよ」
「かしこまりました」
いそいそと片嶋君専用のシェーカーを取り出し、酒を選びながらも、姿勢のいい背中はうきうきと弾んでいました。
そう。片嶋君はレジ係が大好きです。
理由の一つは、お客様が入ってきて一番先に顔を見られるのがこの場所だから。
そして、もう一つは、ウェイティングスペースのお客様のおもてなし係を兼ねているからです。
そんなわけで、普段は自分の持ち場にキリリと座っている片嶋君もこんな時だけは違っていました。
「ショウちゃん、あと5分くらいでお客様がお帰りになるから、会計頼むな」
それがオーナーからの業務命令でも。
「カード払いだったら他の人に頼んでください。誰でも出来ますから」
大好きなお客様が来ている時だけは別なのでした。
オーナー自身がカードの処理をする傍で、グラスに注がれたのは綺麗な色のカクテルでした。
それを小さな手でツッとテーブルの上を滑らせ、大好きなお客様に差し出します。
「サンキュ。いい色だな。片嶋も好きなもの飲めよ」
おごるから、と言われて、普段はキリリとした表情を崩さない猫も思わずニッコリ笑いました。
「ありがとうございます。では、ワインを一杯いただきます」
ごちそうになったのは片嶋君がこだわりをもって店に置いている、安くておいしいワインです。
もちろんこの日のために、そして、サラリーマンである客の財布を気遣って特別に用意したものでした。
これなら一本空けてしまってもそれほど懐は痛みません。
おかげで楽しい時間が過ごせそうだと、片嶋君は満足の笑みを浮かべました。
そんなこんなで、その一角にはまずまずいいムードが流れていました。
しばらくは和やかに二人で世間話をしていましたが。
「な、片嶋」
「はい」
「休みの日って何してるんだ?」
突然の話題転換に片嶋君はちょっと首を傾げました。
そして、心の隅ではほんの少しドキッとしました。
「家の掃除とかネットとかです」
「どこかに遊びにいったりしないのか?」
これはもしかすると、もしかするのでは。
期待は高まり、片嶋君の耳が少しだけピクッと動きました。
そして。
「猫が遠出をすると不審に思われますので」
真面目な顔で返事をした直後、予感は的中。
「じゃあ、たまにはドライブに行かないか?」
これはまぎれもなくデートのお誘い。
日頃一生懸命レジ係をしている自分へのご褒美に違いない。
片嶋君は素直に喜びました。
……もちろん、顔には出さなかったのですが。
「二人だけだと退屈なら他に友達を誘っても―――」
片嶋君が返事をしないのをみかねて、別の提案をしはじめたお客様の言葉を、小さな口が慌てて遮断しました。
「知らない人がいると気を遣うので」
本当は『二人きりがいいです』と言いたかったのですが、それは片嶋君にはちょっと押し付けがましく思えたので遠回しな表現を選びました。
でも、意中の人はやっぱりそれほど気に留めなかったようで。
「じゃあ、二人でいいよな。どこか行きたいところあるか?」
さらりとそんな質問をしてきました。
「場所は別に……でも」
本当はとってもとっても嬉しかったのですが、片嶋君はこの期に及んでちょっと考えてしまいました。
だって。
「……猫とドライブして楽しいですか?」
普通の人はそんなことはしないとちゃんと分かっていたからです。
けれど。
「相手が片嶋なら楽しいと思うよ。弁当作ってやろうか?」
一人暮らしが長いから料理も多少できるけど……という説明を聞きながら、
「お任せします」
片嶋君はそんな返事をして。
それからちょっとだけ俯きました。
もちろんガッカリしたわけではありません。
嬉しくて口元が笑ってしまうのを他のスタッフに見られたくなかったからです。
「じゃあ、日曜の朝10時にこの店の駐車場でいいか?」
「はい。お待ちしています」
もしも特別な目があれば、二人の周りにほのかなハートマークが飛んでいるのが見えたことでしょう。
実際、すっかりいい感じで週末の約束をする二人の遣り取りを北川オーナーは物陰から眺めていました。
そして、一人であれこれと思いめぐらせていたのです。
片嶋君の一番のお気に入りは、お店にとっては決しておいしい客ではありません。
でも。
「……まあ、それでショウちゃんが楽しそうに仕事してくれるなら仕方ないか」
相手は普通のサラリーマン。
とても片嶋君のような大酒飲みの猫を養えるとは思えません。
となれば、自分の酒代を稼ぐため、この仕事をやめることはできないはず。
そこらへんの金持ちに引き取られて二度と店に来なくなるよりはこのまま大勢の客を繋ぎとめてくれる方がずっといい。
オーナーはそう思いました。
そんな理由から、片嶋君が一人になった隙にこっそりとお願いしてみたのです。
「まあ、優しそうなヤツだし、いいんじゃないのか?……でも、仕事は辞めるなよ」
頭の中で計算機を叩きながら、真剣に問いかけてみましたが。
「ご心配には及びません。自立は大事なことですから」
キリッとした様子で返した言葉にオーナーは「よしよし」と頷きながら、片嶋君の恋路の邪魔はしないことに決めたのでした。
こうして片嶋君は大好きな人と週末の約束をしつつ、店を続けることになったのです。
新宿裏通りにある店『Type-B』。
一歩足を踏み入れると異世界のようなその場所は、疲れた人々の心を癒すだけでなく、自立する猫の応援もしているのでした。
-Fin-
|